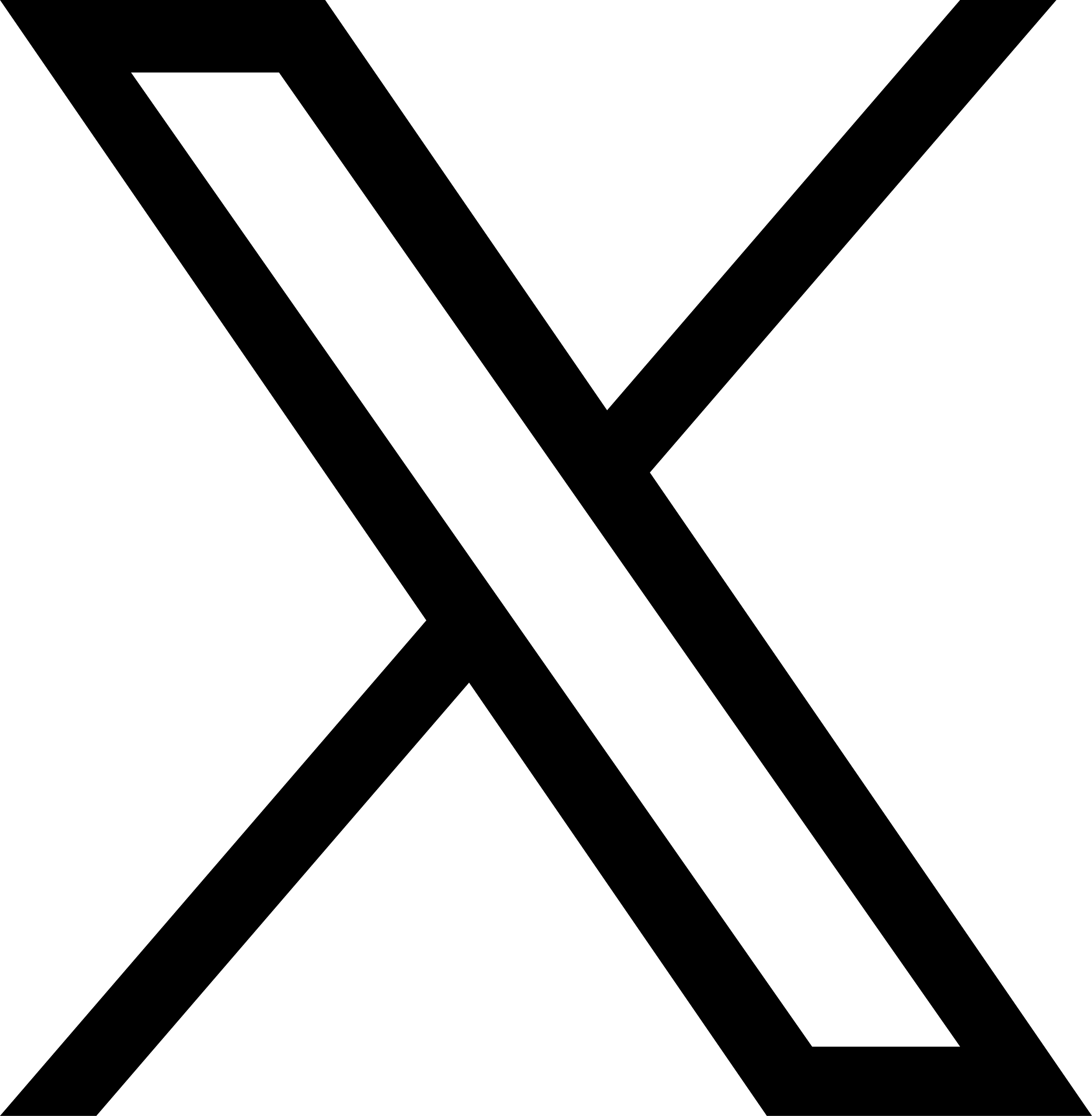AR企画のヒントを解説 「ARで何かやりたい」を形にする
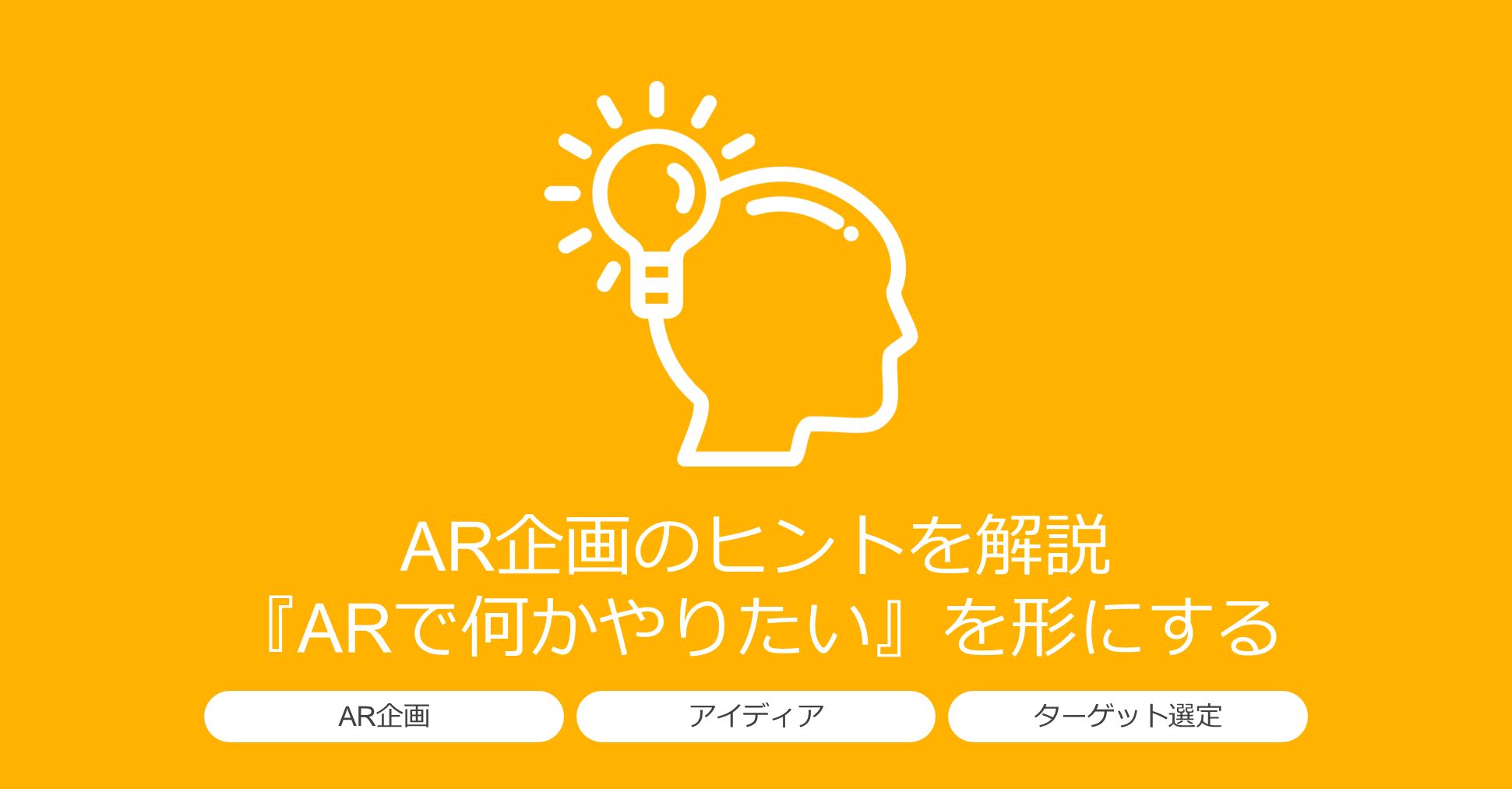
目次[非表示]
- 1.「ARで何かやりたい」と言われて困っていませんか?
- 2.事例紹介:ARを使った学習コンテンツ概要
- 3.分析方法① 5W1H法
- 3.1.5W1Hの分析で明確になるポイント
- 3.2.既存事例を要素に分解
- 3.2.1.<5W1Hで考えるAR学習コンテンツ>
- 3.2.2.<3つの要素に分解して整理>
- 4.分析方法②:メリット・デメリット思考法
- 5.企画を成功させるためのまとめ
- 5.1.企画に盛り込むべき要素
- 6.ARの企画、悩んだらアララにご相談を!
「ARで何かやりたい」と言われて困っていませんか?
クライアントや上司から「ARで何か面白いことをやりたい」「プロモーションでARを使ってみたい」と頼まれたけど、どうやってアイデアを広げればいいのか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
ARは新しい体験を生み出せる技術ですが、AR技術を使って「何をどう拡張するのか?」を考えるのは簡単ではありません。また、専門知識や経験がないために、「アイデアを広げることが難しい」と思い込んでいる方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、実際の事例を「5W1H法」や「メリット・デメリット思考法」を活用し分解することで、AR企画のアイデアを発展させる方法をご紹介します。
これをきっかけに、あなたのプロジェクトが少しでも前に進むお手伝いができれば嬉しいです。
事例紹介:ARを使った学習コンテンツ概要
今回は、ARを使った化学の学習用コンテンツを題材にしてみましょう。
このARコンテンツは、2種類以上の元素が組み合わさって化合物になることを分かりやすく説明するARです。まず元素記号のカードをカメラで映すとカードにあるマーカーを認識し、画面上にその元素が浮かび上がります。さらに異なるカードを組み合わせると新しい化合物が生成されるというものです。
たとえば、水素と酸素のカードを組み合わせると水(H2O)ができ、画面に水のエフェクトが表示されます。視覚的でインタラクティブな学習体験ができるコンテンツです。
このようなARコンテンツを作成するのにどのような観点を考える必要があるのか、「5W1H法」「メリット・デメリット思考法」を使用して考えてみます。
まず、この事例は「何をしたいコンテンツなのか」を想像し、分析してみます。
分析方法① 5W1H法
5W1Hの分析で明確になるポイント
「Who(誰が)」「What(何を)」「Where(どこで)」「When(いつ)」「Why(なぜ)」「How(どのように)」の6つの要素を分解し、整理や企画立案などに使われるフレームワークです。

5W1Hを活用すれば、「やるべきこと」が具体的になり、企画の方向性がぶれにくくなります。
それぞれをどのように使うのか、例を見てみましょう。
*Who (誰に) :ターゲット顧客
(例:20代の若年層、ビジネスマン、主婦)
*What (何を) :提供するサービス・商品
(例:新しいカフェのオープン、アプリの開発)
*Where(どこで) :販売・提供する場所
(例:オンライン、店舗、イベント会場)
*When(いつ) :実施・発売する時期
(例:クリスマスシーズン、新年度の開始時期)
*Why(なぜ) :企画を実施する理由
(例:市場ニーズがある、競合との差別化ができる)
*How(どのように) :実施方法
(例:SNSでプロモーション、イベントを開催)
ARコンテンツを考える際には、「ターゲット」「与えたい効果」「取り入れたい要素」の3つが明確になっていると、内容を作成しやすくなります。
5W1Hの項目ではこれらが該当します。
①ターゲット → 5W1Hの「誰に」
ARを届けたいターゲット層、つまり、ARを使ってもらいたい人物像。
②与えたい効果 → 5W1Hの「なぜ」
ARコンテンツによって与えたい効果や目的。
③取り入れたい要素 → 5W1Hの「どのように」
コンテンツを表現する方法。
既存事例を要素に分解
このように、5W1Hを活用して整理することで、ARコンテンツの設計をより実践的な視点で進めることができます。ここまでご紹介したポイントは押さえられましたでしょうか。
理論だけではイメージが湧きにくいかもしれませんので、さらに理解を深めるために、今回取り上げた事例をこの方法に当てはめてみましょう。
<5W1Hで考えるAR学習コンテンツ>
*Who (誰に)
学生(特に化学を学ぶ中高生や初学者)、教育関係者(教師や教育機関)
*What (何を)
ARを使った化学の学習用コンテンツで元素の組み合わせによる化合物の生成を可視化、インタラクティブな学習体験を提供するコンテンツ
*Where(どこで)
学校の授業(理科・化学の実験や講義で利用)、自宅や学習塾(自主学習や補助教材として活用)
*When(いつ)
化学の授業や学習タイミング(学校の授業、家庭学習、学習イベント)
*Why(なぜ)
化学の概念を直感的に理解しやすくするため、従来の学習方法よりも興味を引き、学習効果を高めるため
*How(どのように)
AR技術を用いて、異なる元素を組み合わせると、新しい化合物が生成されるインタラクティブな仕組み、カメラで元素記号のカードを読み取り
<3つの要素に分解して整理>
今回のケースでは、3つの要素は以下のように考えられます。
①ターゲット
学生や教育関係者
②与えたい効果
原子の結合という抽象的な概念を視覚的に伝える
③取り入れたい要素
インタラクティブであるという点。
カードの上に原子が出現し、カード同士を近づけることで原子同士が合体する仕組みとなっている。
ユーザーはこの操作を通じて、原子の結合を主体的に体験することが可能です。
補足)
この手法がARを採用している理由についても、企画段階で明確にすることが重要です。
今回の事例の場合には、ARを用いることで、従来の平面的な表現では難しい立体的で直感的な操作感を実現でき、ユーザーの理解や興味を深める効果があります。
こうした理由付けは、今回の事例に限らず、どのような企画においても非常に重要であり、ARを活用する意義を具体的に示すことで、企画全体の説得力を高めることができます。
上記のように、他社事例や過去に作成された事例を一旦要素に分解します。
それぞれの要素を、ご自分の企画している条件に入れ替えたり当てはめていくことで、既存事例から要素だけをうまく抽出したアイデアを膨らませることが可能です。
事例をそのまま真似ることなく、効果的なARコンテンツを企画することができます。
分析方法②:メリット・デメリット思考法
次に「メリット・デメリット思考法」を用いて事例を要素に分解し、「企画の実現手段としてARを用いることの利点と注意点」を分析してみましょう。
「メリット・デメリット思考法」とは物事のメリット(利点) と デメリット(欠点) を整理して分析する思考法のことです。物事を客観的に比較し、特定の選択肢の利点だけに囚われることなく、幅広い視点で物事を検討する方法です。

メリット
メリット=ARを使用する利点
ARは、視覚的でインタラクティブな学習体験を提供し、抽象的な概念を分かりやすく伝えます。
安全性が高く、どこでも学べる利便性や、新しい技術としての話題性も魅力です。他分野への応用可能性も広がります。
デメリット
デメリット=ARを使用する際の注意点
一方で、開発コストやデバイスの準備が必要で、物理的な実験の代替には限界があります。競合が多く、認識精度が環境に左右される課題もあります。
以下の表で、化学の学習用コンテンツをARで行った場合に生じるメリットとデメリットを具体的に整理しました。

企画の利点と注意点を分析し、ご自身の企画ににも当てはまる点をあらかじめ想定しておくことで、企画の承認を得る助けとなります。
企画を成功させるためのまとめ
企画に盛り込むべき要素
「5W1H法」では、「誰に」を定めることでターゲットが明確になり、「なぜ」を考えることで得たい効果が見えてきます。そして、「どのように」を出すことで提供方法や必要な要素を導き出すことができます。
「メリット・デメリット思考法」では、利点と注意点を書き出すことで、コンテンツ企画であらかじめカバーしておくべき項目を洗い出すことができます。
以上を踏まえることで、企画の中に盛り込むべき要素や条件に気づくことができます。また、潜在的なニーズやリーチすべきターゲットの深掘りができ、企画に必要な要素を具体化し、より充実した内容に仕上げることができます。
ARの企画、悩んだらアララにご相談を!
ARの企画を行う際には、これらの方法をぜひ活用してみてください。
明確な目的を持つことで、AR技術はその成功を支える強力なツールとなります。
アイデア出しから具体的な企画化までサポートしていますので、 ぜひアララへお気軽にご相談ください。
この記事が、ARコンテンツのアイディアが生まれるヒントとなることを願っています。